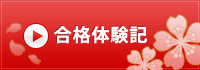現役合格おめでとう!!
2025年 下北沢校 合格体験記

明治大学
文学部
文学科/日本文学専攻
鈴木健太郎 くん
( N高等学校 )
2025年 現役合格
文学部
僕は、中学時代に勉強を疎かにしていたため、高校生になったときの偏差値は40ちょっとと、お世辞にも勉強ができるとは言えない状態でした。そんな僕でも、二つの活用法で東進を使いこなすことで、明治大学に合格することができました。
一つ目の活用法は、とにかく自習室を利用することです。自習室は、騒音もなく落ち着いて、テーブル周りもパーテーションで区切られている半個室状態なので、問題に集中して取り組める環境になっています。僕は通信制の高校に通っていたこともあり、三年生のときは毎日開校と同時に自習室に向かい、過去問演習を行っていました。
二つ目の活用法は、担任助手の方に積極的に相談することです。担任助手の方は大学生の方がほとんどで、受験の経験値が現役高校生とは桁違いです。自学自習で迷ったときや、勉強に対して不安を抱えているときには、担任助手の方に相談することで、的確なアドバイスをもらえます。また、自分の悩みを誰かに打ち明けることで、モヤモヤが晴れ、スッキリとした気持ちで勉強に臨むことができます。担任助手の方に相談することは、勉強効率を上げることにもつながるのです。
僕は将来ゲームクリエイターになって、世界中の人に面白い遊びを提供するのが夢です。一見、受験や大学での勉強と関係ないように見えますが、受験で培った集中力と、これから大学で経験していく様々な出来事は、ゲーム作りで必要な忍耐力と広い視野を養ってくれることでしょう。
一つ目の活用法は、とにかく自習室を利用することです。自習室は、騒音もなく落ち着いて、テーブル周りもパーテーションで区切られている半個室状態なので、問題に集中して取り組める環境になっています。僕は通信制の高校に通っていたこともあり、三年生のときは毎日開校と同時に自習室に向かい、過去問演習を行っていました。
二つ目の活用法は、担任助手の方に積極的に相談することです。担任助手の方は大学生の方がほとんどで、受験の経験値が現役高校生とは桁違いです。自学自習で迷ったときや、勉強に対して不安を抱えているときには、担任助手の方に相談することで、的確なアドバイスをもらえます。また、自分の悩みを誰かに打ち明けることで、モヤモヤが晴れ、スッキリとした気持ちで勉強に臨むことができます。担任助手の方に相談することは、勉強効率を上げることにもつながるのです。
僕は将来ゲームクリエイターになって、世界中の人に面白い遊びを提供するのが夢です。一見、受験や大学での勉強と関係ないように見えますが、受験で培った集中力と、これから大学で経験していく様々な出来事は、ゲーム作りで必要な忍耐力と広い視野を養ってくれることでしょう。

青山学院大学
文学部
史学科
星子友孝 くん
( 日本工業大学駒場高等学校 )
2025年 現役合格
文学部
自分は高校3年生の4月に東進に入学しました。東進に入る前は得意科目の日本史を週に数10分しかやっておらず、苦手科目から目を背け、量、質ともに最悪でした。入学してからは単語帳や受講を始め、少しずつ成績を伸ばし合格することができました。
自分が受験生の時のやってよかったなと思うことが3つあります。1つ目が、家ではなく東進の自習室で勉強したことです。家にはスマホなど誘惑が多くありますが、自習室にはほとんどなく、周りの空気もあり、より集中して勉強に取り組むことができました。
2つ目が9月から受講できる志望校別単元ジャンル演習講座をたくさん解いたことです。志望校別単元ジャンル演習講座は志望校の問題傾向と似た問題に取り組めるもので、基礎の定着、問題傾向の慣れにとても役立ったと思っています。
最後は自分にあった入試方式を探したことです。受験勉強と同じくらい大切だったと思っています。それぞれ得意科目、苦手科目あると思いますが、その得意科目を最大限活かせれば志望校合格に大きく近づけるので、調べないのはとても勿体無いです。
勉強はやったらすぐ成績が伸びるもではなく、本当に伸びてるか分からなく不安な時や、勉強を辞めたくなってしまう時があると思いますが、自分が辛い時は大抵の場合、周りも同じことを思っています。そこで折れないように頑張ってください。
自分が受験生の時のやってよかったなと思うことが3つあります。1つ目が、家ではなく東進の自習室で勉強したことです。家にはスマホなど誘惑が多くありますが、自習室にはほとんどなく、周りの空気もあり、より集中して勉強に取り組むことができました。
2つ目が9月から受講できる志望校別単元ジャンル演習講座をたくさん解いたことです。志望校別単元ジャンル演習講座は志望校の問題傾向と似た問題に取り組めるもので、基礎の定着、問題傾向の慣れにとても役立ったと思っています。
最後は自分にあった入試方式を探したことです。受験勉強と同じくらい大切だったと思っています。それぞれ得意科目、苦手科目あると思いますが、その得意科目を最大限活かせれば志望校合格に大きく近づけるので、調べないのはとても勿体無いです。
勉強はやったらすぐ成績が伸びるもではなく、本当に伸びてるか分からなく不安な時や、勉強を辞めたくなってしまう時があると思いますが、自分が辛い時は大抵の場合、周りも同じことを思っています。そこで折れないように頑張ってください。

立教大学
文学部
史学科
柳沢たま子 さん
( 豊多摩高等学校 )
2025年 現役合格
文学部
私が東進への入学を決めたのは周りより遅かった。勉強時間も周りより少なかったように思える。そして英語の得点がなかなか振るわなかった。そんな中で、自分以外の人に今の状況を客観視してもらい、スケジュールを考えてもらうというのは大事なことだったと思う。それから勉強時間は少しずつ伸びていった。5、6月は1日2・3時間がやっとであったところを10時間はマストで勉強するまで伸ばすことができた。長い勉強時間に慣れることは受験において大変重要だ。
それから、ためになったのは「1日に絶対にやること」を決めておくということだ。私は英単語、熟語、リスニング、長文読解を「絶対にやるべきこと」と決めて取り組んでいた。習慣づけることが大事で、これによって共通テストのリスニングは大きく伸びた。初めは50点前後だったが毎日取り組むことで当日は80点以上とることができた。
受験期は本当に辛かった。毎日落ちるんじゃないかと思う時期もあったし、やる気がない日もあった。とはいえ、ある種の強迫観念に急き立てられて、自習室に向かうことで勉強時間は確保できた。東進が学校の通学路に位置していたので、否が応でも自習室に向かわなければいけないという環境だったのは良かった。そうして勉強を続けたおかげか、成績は順調に伸びた。模試では8割を超えることは無かったのが、共通テスト本番では無事8割を超えることができた。苦手な英語は減点を最小限に抑え、得意科目の国語と世界史で点をとることができたからだ。
世界史は暗記科目なので初めのうちから力を入れ、アドバンテージにできると良いと思う。共通テストから私立大学の受験までの間はあまりない。そのため、共通テスト前までにどれだけ過去問の本を解けるかというのが大事だった。何よりも体験してわかったのが共通テストが終わるとつい燃え尽きてしまうということだ。
そして、予想外だったのが私立入試の間の間の日が一番つらいことだった。やる気はでないのに明日は受験だという状況はかなりメンタルにくる。だから、私は受験が連続で続く方が楽だった。もし連続で入試が続くのでこの学校は諦めようと思う人がいたら体力次第ではあるが少し考え直してもいいかもしれない。
受験は終わり無事大学に受かることができたという喜びは、今まで頑張ってきたからこそ、格別だった。大学に入学したら自分の憧れていた歴史の分野で新たな発見と出会い好奇心をさらに羽ばたかせていきたい。
それから、ためになったのは「1日に絶対にやること」を決めておくということだ。私は英単語、熟語、リスニング、長文読解を「絶対にやるべきこと」と決めて取り組んでいた。習慣づけることが大事で、これによって共通テストのリスニングは大きく伸びた。初めは50点前後だったが毎日取り組むことで当日は80点以上とることができた。
受験期は本当に辛かった。毎日落ちるんじゃないかと思う時期もあったし、やる気がない日もあった。とはいえ、ある種の強迫観念に急き立てられて、自習室に向かうことで勉強時間は確保できた。東進が学校の通学路に位置していたので、否が応でも自習室に向かわなければいけないという環境だったのは良かった。そうして勉強を続けたおかげか、成績は順調に伸びた。模試では8割を超えることは無かったのが、共通テスト本番では無事8割を超えることができた。苦手な英語は減点を最小限に抑え、得意科目の国語と世界史で点をとることができたからだ。
世界史は暗記科目なので初めのうちから力を入れ、アドバンテージにできると良いと思う。共通テストから私立大学の受験までの間はあまりない。そのため、共通テスト前までにどれだけ過去問の本を解けるかというのが大事だった。何よりも体験してわかったのが共通テストが終わるとつい燃え尽きてしまうということだ。
そして、予想外だったのが私立入試の間の間の日が一番つらいことだった。やる気はでないのに明日は受験だという状況はかなりメンタルにくる。だから、私は受験が連続で続く方が楽だった。もし連続で入試が続くのでこの学校は諦めようと思う人がいたら体力次第ではあるが少し考え直してもいいかもしれない。
受験は終わり無事大学に受かることができたという喜びは、今まで頑張ってきたからこそ、格別だった。大学に入学したら自分の憧れていた歴史の分野で新たな発見と出会い好奇心をさらに羽ばたかせていきたい。

立教大学
文学部
キリスト教学科
丸山音乃 さん
( N高等学校 )
2025年 現役合格
文学部
私は高校2年生の1月に東進に入学し、総合型選抜の対策と一般受験の勉強を両立していました。この2つを両立できた理由の1つに、東進の学習環境の良さがあります。まず、大学受験を経験した担任助手の方と一緒に学習計画を立てられたことが大きなポイントでした。何から始めればいいか分からなかった私にとって、担任助手の方と共に計画を立てることでスムーズに学習を始めることができました。総合型選抜との両立は時間がなく、予想以上に大変でしたが、東進の学習システムのおかげで効率よく進めることができました。特に、週に1回行われるチームミーティングでは、自分の学習量を順位で確認できるため、やる気を持続させることができました。これにより、モチベーションが高まり、効率的に勉強を進めることができました。
また、総合型選抜の対策でもお世話になりました。志望理由書の添削をお願いした際、担任の先生は非常に丁寧に指導してくださり、書き方に迷ったときには一緒に考えてくださいました。このようなサポートがなければ、志望理由書にばかり追われ、一般受験の勉強が疎かになっていたと思います。さらに、面接の対策では、実際の流れや雰囲気を担任助手の方から教えていただき、面接の準備を万全にすることができました。その結果、私は総合型選抜で立教大学に合格することができました。総合型選抜と一般の両立ができたのは、東進のサポートがあったからこそだと実感しています。
将来についてはまだ具体的な夢は決まっていませんが、大学ではさまざまなことに挑戦し、自分の興味を広げていきたいと考えています。そして、大学生活を存分に楽しみながら、自分の未来に繋がる経験を積んでいきたいです。
また、総合型選抜の対策でもお世話になりました。志望理由書の添削をお願いした際、担任の先生は非常に丁寧に指導してくださり、書き方に迷ったときには一緒に考えてくださいました。このようなサポートがなければ、志望理由書にばかり追われ、一般受験の勉強が疎かになっていたと思います。さらに、面接の対策では、実際の流れや雰囲気を担任助手の方から教えていただき、面接の準備を万全にすることができました。その結果、私は総合型選抜で立教大学に合格することができました。総合型選抜と一般の両立ができたのは、東進のサポートがあったからこそだと実感しています。
将来についてはまだ具体的な夢は決まっていませんが、大学ではさまざまなことに挑戦し、自分の興味を広げていきたいと考えています。そして、大学生活を存分に楽しみながら、自分の未来に繋がる経験を積んでいきたいです。

東京慈恵会医科大学
医学部
看護学科
石井そら さん
( 駒場高等学校 )
2025年 現役合格
医学部
部活を最後まで続けるか迷っている人や、ヤングケアラーで受験に対して不安に思っている人の参考になれば嬉しいです。私は3年生の9月上旬までサッカー部のマネージャーとして活動していました。夏休みは合宿や試合が多かったため勉強時間は1日6時間程度でした。どの科目も基礎が固まっていなかったので、共通テストの過去問演習よりも基礎の部分のインプットを優先していました。
部活を引退して1か月ほど経った10月には母の体調により、家事と母の世話を担う、俗にいうヤングケアラーになりました。そのため、学校の授業以外での勉強時間は多くて2時間程度でした。他のライバルよりも勉強に割ける時間はどうしても少ないので、効率を意識して勉強していました。例えば、英単語は学校に向かうときの電車で完璧にすると目標を立てて取り組んでみたり、過去問1年分でこの大学の傾向を見つけると意識して取り組んだりといった感じです。私はどの大学も2年分しか演習できませんでしたが、大学を4つ受けてすべて合格することが出来ました。
また、面接の戦略としては、緊張してしまうと思いますが笑顔が大切です。一応大学ごとにアドミッションポリシーがありますが、結局は筆記の試験では測れない人間性を見たいから面接があるので、この子なんか雰囲気いいなと思ってもらえればこっちの勝ちです。私自身面接の一番初めに「笑顔が素敵ですね。あなたの笑顔を見るだけで患者さんの気持ちが楽になると思う。」と言われました。質問に対する答えをたくさん頭に入れてから面接に臨みましたが、定番な質問4つで面接は終わりました。面接はそんなもんです。気負いすぎなくて大丈夫です。
部活を引退して1か月ほど経った10月には母の体調により、家事と母の世話を担う、俗にいうヤングケアラーになりました。そのため、学校の授業以外での勉強時間は多くて2時間程度でした。他のライバルよりも勉強に割ける時間はどうしても少ないので、効率を意識して勉強していました。例えば、英単語は学校に向かうときの電車で完璧にすると目標を立てて取り組んでみたり、過去問1年分でこの大学の傾向を見つけると意識して取り組んだりといった感じです。私はどの大学も2年分しか演習できませんでしたが、大学を4つ受けてすべて合格することが出来ました。
また、面接の戦略としては、緊張してしまうと思いますが笑顔が大切です。一応大学ごとにアドミッションポリシーがありますが、結局は筆記の試験では測れない人間性を見たいから面接があるので、この子なんか雰囲気いいなと思ってもらえればこっちの勝ちです。私自身面接の一番初めに「笑顔が素敵ですね。あなたの笑顔を見るだけで患者さんの気持ちが楽になると思う。」と言われました。質問に対する答えをたくさん頭に入れてから面接に臨みましたが、定番な質問4つで面接は終わりました。面接はそんなもんです。気負いすぎなくて大丈夫です。